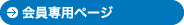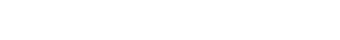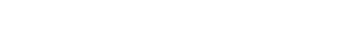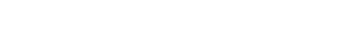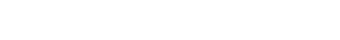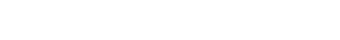活動成果
2025.04.09
活動成果
【報告】熊本大学 一般社団法人メディポリス医学研究所メディポリス国際陽子線治療センター・薬局研修
【日 程】2024年11月14日(木)~15日(金)
【研修先】・一般社団法人メディポリス医学研究所メディポリス国際陽子線治療センター
・てらわき薬局城西
【参加者】熊本大学生:10名 東京大学生:3名 合計13名
随行教職員 :1名
講 師 :4名
【概 要】
医療の革新的な進歩により、多様な新規がん治療法が開発され、がん患者が様々な治療戦略の中から最適 な治療法を選択できる時代になりつつある。本研修では、薬剤師の観点から最新のがん治療の動向・現状を把握し、個々の患者に最適ながん治療を実施するための知識を習得することを目的とし、がん治療における最先端の陽子線治療を実施している「メディポリス国際陽子線治療センター」のご協力のもと、下記の通り研修を実施した。
【講演会】
・荻野尚 先生(センター長):センターの概要説明・陽子線治療の原理
・湯之前清和 先生(事務局長):センターにおける薬剤師の役割
・持留隆伸 先生(センター薬剤科):薬剤師によるキャリアパス
(先輩薬剤師の立場から参加学生との意見交換会)
【施設見学】
・陽子線照射回転ガントリー治療室・患者処置室での陽子線治療デモ
・患者専用宿泊施設紹介(メディカルリゾート【HOTELフリージア】)
【てらわき薬局城西・薬局見学】
・井上鈴菜先生による薬局見学、近未来の薬剤師像についての意見交換
【実施した感想】
昨年に引き続き、現地開催の研修を実施することができた。2017年度から継続して本研修を実施しているが、薬学コアカリキュラムでは学べない最新のがん治療の現状に触れ、本年度も学生達にとってとても有意義な時間となったと思われる。最新の治療に加え、がん治療全般において薬剤師に求められる知識、チーム医療における薬物治療のエキスパートとしての役割を認識するとても貴重な機会となったと思われる。また、先輩薬剤師のキャリアパスに関する講演・意見交換、加えて、てらわき薬局城西の薬局見学は、各学生の目指す将来像について議論するきっかけとなり、今後の薬学部での学びに対するモチベーションも向上していたようである。
最後に、本年度もメディポリス国際陽子線治療センター・てらわき薬局城西の先生方に、多大なるご支援・ご協力を賜り誠にありがとうございました。本研修にご協力いただいた全ての皆様に対して、この場をお借りして感謝申し上げます。
【参加学生の感想】
➀1日目は、荻野センター長の講演から始まった。がん治療の基本知識に加え、陽子線治療に関する詳細な解説や症例紹介、さらにその課題についてのお話があった。陽子線治療は、X線治療と同等の治療効果を持ちながら正常組織への影響を抑えられる点で非常に魅力的であり、今後普及が期待される治療法であると感じた。一方で、金銭面での課題は大きく、保険適用範囲が限られている現状が普及の壁となっていることも指摘された。こうした課題が解決され、治療の選択肢の一つとして広く認識されてほしいと感じた。薬剤師の湯之前先生の講演では、病院薬剤師のあり方について学んだ。頭頸部がんの陽子線治療に伴う口腔粘膜炎リスクの低減に向けた対策や、造影剤による副作用への対応策が具体的に示された。特に、口腔ケアに関しては、歯科でしか保険適用にならない薬を使用するために地域の歯科医師会と連携したと伺い、他職種連携・地域連携の重要性を感じた。施設見学ではなかなか見る機会のない陽子線治療の治療室・回転ガントリー・シンクロトロンを見ることができた。特に乳がん治療技術は創意工夫に富んでおり、感銘を受けた。リゾート滞在型治療施設の見学では、患者のQOL向上を図る設備やサービスについて知ることができた。実際に自身も宿泊し、綺麗な部屋・美味しい食事・温泉によって癒された。治療そのものだけでなく、滞在環境の整備が患者に与える精神的・身体的な影響の大きさを実感した。2日目は、薬剤師の持留先生の講演から始まった。薬剤師としての取り組みや挑戦を具体例とともに学んだ。「好きを仕事に取り入れる」という姿勢が特に印象的で、先生の場合は興味のある漢方薬を用いたがんサポートケアに取り組んでいた。また、学校薬剤師の必要性についてのお話が印象に残った。もちろん薬剤師として薬の正しい知識を教えることが大切だが、それだけではなく、子供たちや周囲の大人たちとどう向き合うべきかを考える必要があるなと感じた。その後訪れたてらわき薬局では、調剤業務の機械化の現場を見学した。自動分注機や調剤ロボットなど、最新の設備が導入されており、特に調剤ロボットは初めて目にするものであった。24時間対応可能な薬の受け取りシステムは、患者の利便性を大きく向上させる画期的な取り組みだと感じた。本プログラムを通じて、病院薬剤師や地域薬剤師の役割の広がり、患者のQOL向上を目指す姿勢、そして最先端技術の活用による業務効率化について多くを学ぶことができた。
➁今回の研修で得られた知見・感想を以下の5点に分けて記述する。
(1) 粒子線治療の現状:粒子線治療の特筆すべきメリットは侵襲度の低さ、QOLの良さ(*基本的には外科手術と同程度だが、前立腺がんにおいては明確に粒子線の方が優れていること)にある。もとより放射線治療は他の療法に比して侵襲度の低いものではあるが、粒子線治療はブラッグピークの利用により高効率の腫瘍選択性を実現できている。また、陽子線であればその軽さを生かして患者個々人に最適な方向から照射可能であり、重粒子線であれば生物学的効果の大きさを生かして短期間での治療が可能となる。直感的には、照射口ではなく患者の方を回転させることで、重粒子線も陽子線と同様に最適な方向からの照射が可能なようにも思えるが、物事はそう単純ではないようだ。
メリットだけでなく、課題も多く存在する。最も大きな課題は治療施設の少なさであろう。現在、日本には粒子線治療を行うことのできる施設が26か所しか存在しない。世界的には比較的多い方ではあるが、例えば九州であれば佐賀県と鹿児島県に各1施設ずつしか存在しない。また、大抵の施設は交通アクセスも良いとはいえない。故にこそ後述するようなメディカルリゾートが重要になってくるわけだが、全国的には治療へのアクセシビリティがまだまだ低いと言わざるを得ないだろう。粒子線治療施設の新造には膨大な金額と広大な土地が必要であるため、この課題は今後しばらく残存し続けると予想される。それに加えて医療費の問題もある。粒子線治療の費用は約300万円であり、保険適応の範囲はまだ狭い。今後適応範囲が拡大されていくとしても、国民の負担は大きくなるかもしれない。諸々を考慮すると、粒子線治療が人口に膾炙するにはもう少し時間がかかりそうだ。とは言え、学術的には非常に興味深い先進医療の一つである。PBCTや免疫チェックポイント阻害剤併用時のアブスコパル効果増強など、粒子線治療に関連する研究の動向には注目していきたい。
(2) メディカルリゾートの有用性:メディポリス国際陽子線治療センターの最大の特徴は、メディカルリゾートが併設されていることにある。正直なところ、研修に赴く以前にはその価値を正しく認識できていなかったが、メディポリスにおいてこのリゾートホテルが併設されていることは極めて有用だと感じた。このメディカルリゾートの有用性は複数の要素が関連することで成立している。まず大前提として、先述したように粒子線治療の侵襲度は低く、患者の生活を強く拘束するようなものではない。したがって、患者に入院の必要は無く、通常は治療の度に通院するのが妥当である。しかしながらメディポリスのような粒子線治療施設は大抵アクセスしにくい場所に存在する。実際、メディポリスは鹿児島市内から電車で1時間ほど移動し、更に車で15分かかる山上に存在する。メディポリスを利用する方の多くにとって、治療施設の傍で宿泊できることの有用性は想像に難くない。さらにメディポリスが位置する指宿市は温泉で有名な観光地であるため、治療ついでの観光を可能にするという意味でもリゾートホテルは便利だ。また、メディポリスに特徴的な治療法として乳がんの陽子線治療が存在しており、この治療法に対しても宿泊施設が有用となっている。この治療においては乳房を固定する器具を利用するが、その器具の取り外しには水が必要となる。つまり、治療後に温泉に入浴することで、その器具を効率よく外すことが可能になっている。これらの有用性は、メディポリスにおける治療患者数の多さに直結しているのかもしれない。公益財団法人 医用原子力技術研究振興財団の公開している資料(https://www.antm.or.jp/information/clinic/file/ryuusisen-kanja_2024.pdf)によると、メディポリスは他の施設よりも比較的多い治療患者数を示しているようにも思える。当然ながら、各地の人口分布や医療充実度等も考慮しなければ正確なところは評価不能だが、実際に現地に赴いた身としては、患者目線でメディカルリゾートの併設は非常に有難いことだと感じられた。しかし、がん治療患者と温泉との相性に関しては懸念点もある。粒子線治療においては化学療法との併用も想定されるが、そのような患者が温泉を利用するとなると、免疫抑制による患者の易感染リスク、および非患者の抗がん剤暴露リスクを考慮せねばなるまい。基本的に温泉の利用者は患者とその家族などが主であるとは言え、これらに関する情報提供が少し物足りないような印象は感じた。
(3) 薬局における機械導入の在り方:てらわき薬局城西においては、薬局における対物業務の大半が機械によって自動化されていた。今年私が実習に赴かせていただいた薬局でも単純な分包作業や軟膏の混合は機械が担っていたが、今回の研修では全自動水剤分注機や散薬調剤ロボット、BD Rowa™ システムによる医薬品全自動管理を初めて目にすることができた。たかだか数か月の実習を経験しただけの身ではあるが、薬剤師にとってこれらの機械は非常に便利なものであると思われる。特に水剤や散剤の調整は通常であれば1人の薬剤師を一定時間拘束してしまうものであり、この作業を完全に機械が代替してくれることのメリットは計り知れない。また、24時間自動払い出しシステムが患者と薬剤師の双方にとって非常に有用であることは自明である。機械の有用性を認識できたと同時に、いくつか見えてきた課題もある。まず大抵の機械に通じる問題点として、取り扱い可能な品目数の制限が挙げられる。仮に私が実習に赴いた薬局に貯蔵されていた医薬品全種を機械にストックさせようとすると、機械が何台必要になるのか途方も付かない。もちろん一部を機械にストックできるだけでも有用ではあるが、てらわき薬局城西のように小規模であるか、取り扱う医薬品の種類が限定されている薬局でなければ効果的な運用は厳しいだろう。それに加えて、そもそも機械を配置するスペースの問題もある。機械本体を置くスペースは当然としてコンセントの数や位置も考慮せねばならず、BD Rowa™ Pickup Semi-Outdoorは店舗外壁面に設置せねばならない。すでに営業中の薬局に後から機械を導入することは極めて難易度が高いだろう。また、実運用的な面では、散薬調剤ロボットに溜まっていくデッドストック対策として高頻度で散剤を機械に詰める作業が必要になるだろうし、処方箋受付枚数の多い薬局ではBD Rowa™ システムが律速段階になってしまう(複数の薬剤師が薬品棚から手動で集める方が明らかに速い)ことも考えられる。
以上の諸々と導入費用を考慮すると、そう単純に機械導入を礼賛できるわけではないのだろうと感じた。
(4) 地方医療の今後について:メディポリスにおける研修では地方における人材の少なさを強く感じた。近年は「薬剤師の総数が飽和に向かっている一方で、地方での薬剤師数が足りていない」という話もよく耳にするが、薬剤師だけでなく医療に携わる人材が十分ではないということを感じさせられた。本研修中の講演会にて、メディポリスにおける薬剤師業務は実質的に持留氏のワンマン体制だと伺った。それはまだよい。人材が多いに越したことは無いが、過剰なのもまた問題である以上、ワンマンでも問題なく薬剤師業務がこなせているのであればよい。しかしながら、メディポリスが2011年から運用されている施設にも関わらず、患者の急性期対応に必要な医薬品の使用プロトコルやNSTの運用が近年まで用意なされていなかったことには驚きを感じずにはいられなかった。もしかしたら医療従事者の意識の問題に起因する部分もあったのかもしれないが、仮にそのような側面があったとしても、人材が豊富であればより早期から対応できた課題であったことだろう。いま日本全体として高齢者増加・労働人口減少・都市部への人口集中が継続しているなかで、地方の人材不足はより深刻なものになっていくことが予想される。地方の中枢都市ならまだしも、指宿市のような人口減少地域では猶更であろう。メディポリスのように重要な医療施設を長期的に存続させるためには、このような人材不足の問題にも対処していくべきなのだろうが、これは個々人には対処不能な問題であると感じる。地方医療の将来はどうなっていくのだろうか…。
(5) 薬剤師のあるべき姿:てらわき薬局城西での研修では、「対人業務」の重要性が語られていた。いま全国的に「『対物業務』よりも『対人業務』に集中していくべき」というスローガンが掲げられている。先述したような機械導入による業務効率化や薬剤師の飽和を考慮すれば正にその通りだとは思う。しかしながら、「対人業務」も当然重要だが、また別に重要な「対物業務」があると感じている。それは単なる調剤だとか医薬品管理とかではない。それは例えば、病院実習で目にしたTDMやがん専門薬剤師の豊富な知識をもとにしたチーム医療、また、持留氏がメディポリスで行ったNST設営など、対人業務とは全く異なる方向で医療を向上させる業務である。「対人業務」よりも難易度が高く、残念ながら全薬剤師が出来るものではないだろう。しかし、どうせ理想を掲げるのであれば、これくらい大きいほうが良いだろうし、これから日本の医療・地方の医療に真に求められているのはこのような対物業務を行う能力ではないだろうか。仮に私が将来的に薬剤師として働くのであれば、そのような薬剤師を目指したいと考える。
➂11月14日から15日にかけて、メディポリス国際陽子線治療センターにて研修を行った。研修内容は陽子線治療の概要(機序や実際の治療例)と実際にセンターで勤務している薬剤師の方々が陽子線治療へ薬剤師としての関わり(副作用軽減のための薬剤選択・地域歯科との連携など)に関する講義を受けた他、センターの治療室や回転ガントリー、サイクロトロンの鹿児島中央駅付近の寺脇薬局の見学も行った。
研修で印象に残ったこととしては、質疑応答中に少し触れられたアブスコパル効果に関してである。恥ずかしながらこちらの勉強不足でそのような効果の存在をこの研修に至るまで知らなかったのだが、「放射線を照射していない部位でも腫瘍が縮小する」という効果のようであり、免疫チェックポイント阻害剤と陽子線治療の併用により、相乗的な効果が見込まれると述べられていた。近年の知見では、免疫チェックポイント阻害剤によりtumor antigen-specificなT細胞が活性化するためこういった現象が起きるとされている。マウスを用いた実験では、致死量の放射線を照射して免疫細胞を除去するというものがあるため、放射線照射は免疫細胞にダメージを与えるという印象があったが、治療に最適化された線量の照射ではむしろ免疫細胞が活性化されるのかもしれないと感じた。陽子線治療の副作用で、口内炎が起きたという報告もあったが、こちらもそれで説明出来るのではないだろうか。余談ではあるが、薬剤師の方から学校薬剤師の業務も行なっているというお話も伺った。学校薬剤師というとプールの水質や照度の検査などを行うという印象があったが、どうも昨今問題となっているオーバードーズに関する教育及び啓発を行っているとのことで、学校薬剤師の業務を対物から対人になっているのかとも感じた。薬局の見学でも調剤補助機械(補助とついているのがミソでこの機械を用いて調剤ミスが発生したとしても機械のメーカーは責任を取らないということのようである)の導入が進んでおり、導入による人件費の削減も可能となったという。ただ地域ブロック長の方も述べていたが機械も上手く使えないと高い置物になってしまうため、どう使いこなすかを考えるのも薬剤師の役目であると感じた。陽子線治療という馴染みのない治療の現場を体験できる貴重な経験であると同時に、薬剤師としての今後のキャリアを考えさせられる機会であった。
➃本研修では、メディポリス国際陽子線治療センターにて陽子線治療やその中で薬剤師が実施している業務や取り組みについて勉強させていただいた。荻野先生のご講演では、がんやその治療法、陽子線治療の特徴(効果や副作用など)についてご教示いただいた。陽子線治療は、重粒子線治療に比べて治療期間が長くなりやすい点で劣る一方で、360°のいずれの角度からでも照射が可能であるため、病変に柔軟に対応できる点で優れているということを学んだ。実際に陽子線治療室で、照射口が回転する様子や陽子線の線量分布をがんの形状に合わせて調整する様子を見学させていただいた。治療中に痛みを感じない点や1回の照射が短時間で完了する点、他臓器の障害が少ない点は陽子線治療の大きな強みだと感じた。湯之前先生のご講演では、陽子線治療に伴う口腔粘膜炎に対して質の高いケアを提供するための体制(医科歯科連携)や、造影剤による副作用を軽減するための取り組み(飲水奨励やステロイド前処置など)について詳細に学ぶことができた。それらの多くは、これまでに先生方が実施された研究成果に基づいており大変貴重な知見をご教示いただいた。臨床業務の中で直面する課題や疑問に対して臨床研究を実施することで解決策を見出し、より効果的な医療の提供を実現する体制はとても魅力的だと感じたし、私も研究活動への更なる意欲向上に繋がった。持留先生のご講演では、がん治療をサポートするための薬剤師としての取り組みについてご紹介いただいた。その内容として、有効性や安全性が懸念される薬剤に対処すべく作用機序の異なる薬剤を新たに導入されたことや、単剤で複数の症状に治療効果が期待でき、併用禁忌・注意が少ないという利点を活かして漢方薬による治療も推進されていることを伺った。2日目に見学させていただいた、てらわき薬局城西では、機械の導入により調剤を中心とした様々な対物業務で効率化が図られていた。中でも、調剤時に指定の錠剤を自動で捜索してくれるシステムは非常に画期的だと感じた。機械の方が人間よりミスが少ないため、正確さが求められるルーティンワークでは機械の力を借り、薬の専門家である薬剤師は患者個々の状況に合わせた適切な支援の提供に注力するという体制は、適材適所の考え方に基づいており、とても効果的だと思った。本研修を通して、がん治療における陽子線治療の位置づけや、今後の薬剤師に求められる能力について幅広く勉強させていただいたことに感謝申し上げます。
➄2024年11月14・15日に開催された「メディポリス国際陽子線治療センター研修」に参加し、陽子線治療の特性や先進的な薬局業務について学びました。初日、荻野センター長の講演では、陽子線治療ががん細胞を正確に狙い撃ちし、正常組織へのダメージを最小限に抑えられる治療法であることを学びました。従来の放射線治療と比較し、副作用が少なく、患者のQOLを維持しながら治療できる点が特に印象的でした。また、陽子線治療は、乳がんや前立腺がんをはじめとした治療に適用され、保険適用範囲も拡大していますが、その認知度向上が課題であると感じました。続く湯之前事務局長の講演では、薬剤師が中心となり実施した口腔ケアや造影剤副作用対策について学びました。陽子線治療に伴う口腔粘膜炎を軽減するため、医科歯科連携を推進し、患者のQOL維持に努めた取り組みが紹介されました。また、造影剤の副作用を抑えるための飲水指導やステロイド前処置の重要性についても言及され、薬剤師が多職種と連携しながら医療環境を改善している様子に感銘を受けました。施設見学では、陽子線治療のための巨大な装置や治療室を見学しました。治療そのものは短時間で行われ、患者の身体的負担が軽い一方、高度な設備とメンテナンスを支える技術者の存在が重要であると実感しました。さらに、施設内に併設されたリゾート型ホテルでは、患者が自然の中でリフレッシュしながら治療を受けられる環境が整えられており、患者の心身のケアにも配慮された設計に感銘を受けました。2日目のてらわき薬局見学では、最新の機械を導入した調剤業務を目の当たりにしました。機械化により調剤ミスを防ぎ、薬剤師が処方監査や服薬指導に集中できる環境が整えられていました。また、24時間薬の受け取りが可能なシステムが患者の利便性を向上させている点も印象的でした。これにより、薬剤師が対人業務により時間を割けるだけでなく、患者一人ひとりに寄り添う医療を実現できると感じました。今回の研修を通じて、薬剤師の業務が単なる薬の調剤にとどまらず、患者の生活を支える多面的な役割を担っていることを再認識しました。特に、問題解決能力や多職種連携の重要性を学び、今後の自身のキャリア形成においても視野を広げるきっかけとなりました。最新技術と人間的な配慮を融合させた医療現場の未来を垣間見ることができた貴重な体験でした。
⑥11/14~15にかけてがん陽子線治療を専門とする「メディポリス国際陽子線治療センター」にて行われた研修に参加した。今回の講義では、陽子線治療の基礎から臨床での応用例、がん陽子線治療における薬剤師の取り組みなど、幅広い内容を学んだ。その中で、特に印象に残ったのは、陽子線治療の副作用予防・治療における医療連携についてである。陽子線治療は、がん細胞が存在する場所でブラッグピークが発生するように照射角度、距離を調節することで正確な照射ができるため、周囲の健康な組織へのダメージを最小限に抑えられると学んだ。陽子線照射の際、陽子線の照射漏れがあってはならないため、がんの大きさよりやや広い範囲を陽子線で照射する。そうすると、がん細胞の近くに存在する正常な細胞もがん細胞と一緒に死んでしまうことになる。講義の例では、頭頸部がん治療において、陽子線によりがん細胞だけでなく、正常な口腔粘膜まで陽子線照射の影響がおよび口腔粘膜炎を発症してしまった患者への口腔ケアに関する医療連携についての講義があった。がん治療による口内炎の痛みを緩和する薬剤として、「エピシル」という創傷を保護する口腔溶液が存在する。この薬は陽子線治療によって発生した口腔粘膜炎治療への使用が期待されたが、この薬剤は歯科診療報酬で特定保険医療材料として保険適用されるため、歯医者による処方でなければ保険適用することができず、治療施設内に歯科が設置されていないため、今回のようなケースで使用することができない。そこで、施設周辺に存在する歯科医院と連携することで連携先の歯科で診察を受けてもらい、エピシルを処方してもらうことで、陽子線治療による口腔粘膜炎への治療に使用することができるようになった。また、この連携により定期的な口腔内のメンテナンスが入ることで口腔ケアの質が向上し、口腔粘膜炎の程度を抑えることができるなど、様々なメリットがあった。今回の例から、医療施設単体で完結させようとするのではなく、医療施設間でお互いの不足している部分を補い合うことは非常に重要で、以前からよく言われている医療施設間の連携を常に業務の念頭に置いて仕事を進めていくことが重要だと感じた。2日目で訪問した「てらわき薬局」では、錠剤・散剤一包化の機械だけでなく、液剤調剤やピッキングまで機械化されており、世の中で言われている「対物から対人へ」がより実装されている薬局であると感じた。機械化が進むことで薬剤師が調剤をしない時代が来た際に、薬の知識だけでなく、患者さんとの信頼関係をうまく構築することができるようなコミュニケーション能力を磨いていかなければならないと感じた。
➆陽子線治療について:がんの放射線治療において、線量が必要となることが分かった。X線と陽子線は同等の効果を持つが、陽子線治療では正常組織への障害を抑えつつ、主要部位で抗腫瘍効果を発揮できるように、正常組織への線量を減らし、腫瘍への線量集中率を上げることができるということを知った。陽子線治療は保険適応が広がってきており、患者様が少ない自己負担額で治療を行うことができるようになってきている。陽子線治療を推奨するかどうかは意見が分かれている部分があるので、がん治療を検討するときはセカンドオピニオンを受けることも重要であると分かった。
薬剤師としての取り組み:頭頸部がんに対する陽子線治療では、口腔粘膜炎をおこしやすい。口腔粘膜炎がおこると、強い痛みにより食事や口腔ケアが困難になる。口腔内膜炎の炎症に対して有効なエピシルという薬は保険適応が歯科のみであったため、陽子線治療後に処方することができなかった。そのため、医科歯科連携として頭頸部がん治療の前に歯科を受診してもらい、エピシルを処方してもらうことで頭頸部がん治療後に口腔粘膜炎を発症したとしても、エピシルを使用してもらい、痛みを抑えることができ、口腔ケアが可能となり、食事ができないつらさを感じることが少なくなったという。このように、患者様の様子に気を配り、問題を見つけ、解決策を考えることで、治療後の患者様のさらなるQOL向上につなげることができる。薬剤師として、薬物治療で問題解決に貢献できる手段はないか常に模索することが重要であると感じた。
てらわき薬局城西の見学:てらわき薬局では、水剤・散剤・錠剤を自動で準備する機会が導入されていた。機械導入は対物業務を減少させ、対人業務に時間を確保するという大きな役割を持つ。また、人件費の削減にも大きく寄与することができる。また、とても興味深く感じたのが、患者さんが営業時間外に薬を取りに来ることができることである。患者様から送られてきた処方箋のデータをもとに薬を準備し、薬を薬局の外側にある機械の中に入れておき、オンラインで服薬指導を行う。そして、患者様が時間外に来た時に、事前に送られていた番号を機会に打ち込むことで、自動で薬を取り出してくれる。このため、患者様は時間外に薬を受け取ることができ、服薬指導も済ませているので、すぐに薬を使い始めることができる。このように、機械をうまく利用することで、患者様の生活リズムに合わせた対応を実現することができる。患者様の生活リズムに合わせた薬局業務ができるようになることで、重宝される薬局になれるのだろうと感じた。
➇メディポリス国際陽子線治療センターで、荻野先生や湯之前さん、持留さんの講演や陽子線治療施設見学や患者さんの宿泊するホテルなどを見学でリゾート滞在型の陽子線治療について学んだ。荻野先生の講義では、陽子線治療の最大の特徴は線量集中性で、正常組織への影響を減らし、腫瘍細胞への影響を最大限に発揮するということを学んだ。またこの治療のメリットとして、治療計画通りに行えること、仕事や趣味をしながら行えることで患者さんのQOLを維持することができることだということを学んだ。湯之前さんと持留さんの話では、薬剤師として処方箋通りただ薬を処方するのではなく、患者さんの治療が円滑に進むように、医者や看護師などの他の医療スタッフや地域の他の病院などと連携し、様々な取り組みをしていくことの重要性について学んだ。そして、メディポリス国際陽子線治療センターで治療されている患者さんが宿泊されているホテルに実際に宿泊させていただいて、廊下などで交わした患者さんとの挨拶などから患者さんから明るい印象を受けた。それは患者さんのQOLの高さからくるものだと思うので、リゾート滞在型のがん治療の良さを実感することができた。 次に訪れた薬局では、薬局の機械化を感じることができた。この薬局では、薬の調剤、処方、薬の管理のほとんどを機械が行っていた。薬局の方によると、機械化のおかげで調剤にかかる時間は人が行っていたときの3分の1ほどになり、その浮いた時間を患者さんとの会話や服薬指導などのコミュニケーションに充てることができて、かかりつけ薬剤師としての役割を果たすことができるそうだ。今回の研修で、新たな治療法である陽子線治療について、またその治療の様子を知ることができた。そして、病院薬剤師、薬局薬剤師それぞれが果たすべき役割と実際に行うべきことについて、現役の薬剤師の方の話を聞くことができてとても良い機会となった。
⑨メディポリス国際陽子線治療センターで、講演や見学を通して、陽子線治療の基本知識、X線治療や手術、化学療法との違い、良さを知ることができました。陽子線治療は、水素原子イオンをシンクロトンという加速器で光速近くまで加速し、がん病巣に向けて照射します。陽子線は、がん病巣のみを狙い撃ちできるため、正常組織への線量を抑えた上で、腫瘍に対して線量集中することができ、X線治療や手術、化学療法で起こりうる副作用を軽減できます。また、ピンポイントでがん病巣を狙えることで、X線では照射部位の周りの組織や臓器への影響が大きかったが、それらの影響を抑えることができます。さらに、陽子線治療は1日1回10〜30分程度で終わり、治療中に熱や痛みを感じることはないので、患者さんへの負担も最小限に抑えられる治療と言えます。メディポリスは、治療施設の充実さはもちろんですが、ホテルが先に建てられたということもあって、宿泊施設や温泉、その周りにある自然なども含め、患者さんにとって最適な環境であると実感しました。日本人の2人に1人が一生の間にがんになると言われている中、多くが公的保険の対象となっており、腫瘍への効果も高く、適応の制限が少ない陽子線治療は、未来の医療の質向上に貢献していると言えます。がん治療のサポーティブケアとして、漢方薬も取り入れていることに驚きました。基本的に長期的に服用して効果を期待するものであり、様々な症状に対して効果のあるものなので客観評価が難しいという課題もありますが、薬価が安い、重篤な副作用が少ない、併用禁忌や注意の薬剤が少ない、食欲不振、全身倦怠感、末梢神経障害などの難治性の症状に対応可能といった多くの利点もあり、期待できる治療とも言えます。薬局見学では、実習を経験していない私にとって、実際の薬剤師の業務を見学できる大変いい経験となりました。ある程度は想定していましたが、想定を超えるほど業務を機械に頼れる環境にあり驚きました。しかし、機械を使うのは人間であり、正しい使い方を知らないと、それこそ機械に乗っ取られる時代が来てしまいます。また、機械の使用によって生まれた時間を対人業務に割いて、より質の高い服薬指導、情報整理、医師へのフィードバックが出来るのが現代の時代だと学ぶことができました。
⑩11/14(木)、15(金)の2日間、メディポリス国際陽子線治療センター・薬局研修に参加した。メディポリスは緑に囲まれ、海や指宿の街並みを見渡せる立地と、巨大な陽子線治療の機器や宿泊施設を完備した素晴らしい場所であった。荻野センター長の講演では、がんに関しての基本的な知識や治療の歴史、陽子線治療についての概要などをお話していただいた。陽子線治療は仕事や趣味を止めることなく、おおむねスケジュール通りに治療が可能であることや、放射性抵抗性腫瘍でも治すことができることから、今後のがん治療の選択肢として普及していく可能性を感じた。湯之前事業推進本部長の講演では、陽子線治療における口腔粘膜炎の対処について、医科歯科連携構築の提案とその実行についてのお話をしていただいた。口腔粘膜炎の治療薬剤であるエピシルが、放射線科は保険適用外だったことからそのアイデアを思いついたとのことだったが、患者さんを第一に考えたその実行力に驚かされた。薬剤科の持留先生の講演では、学校薬剤師の観点から、近頃問題となっている若年層のオーバードーズに関して、小学生などに薬に関する正しい知識や健全な薬学教育を行う重要性を教えていただいた。また、漢方薬を用いたがん患者のサポーティングケアについても話していただいたが、薬剤師が調剤などの仕事にとどまらず、様々な問題を解決しうる人材になれることを再確認でき、今後の学生生活のモチベーションが高まった。てらわき薬局での意見交換会と薬局見学では、機械化が進む薬局内部を目の当たりにしたり、一緒に研修に参加していた東京大学の5年生を交えてグループワークを行ったりして、今後の薬剤師に求められるスキルや近未来の薬局の在り方を深く考えることができた。薬局薬剤師の方に、業務について直接教えていただいたことからもかなり刺激を受けた。最後に、この研修に参加させていただき本当にありがとうございました。
⑪研修の1日目には、メディポリス国際陽子線治療センターの荻野センター長、湯之前事業推進法部長より講演があり、2日目には、持留職員より先輩薬剤師のキャリアパスの講演があった。その後、てらわき薬局城西に移動し、株式会社大賀薬局の方から薬局の見学、グループワークを行っていただいた。まず、荻野センター長のお話では、がんに対する陽子線治療のメリットや他の放射線治療との違いなどを教わった。放射線治療での晩期有害事象を抑えるためには線量集中性がキーワードとなるが、陽子線治療ではブラックピークを腫瘍の大きさに応じて拡大できるので正常細胞への悪影響が少なく、晩期有害事象や放射線誘発がんの発生頻度が通常の放射線治療よりも少ないことがよく分かった。また、X線と陽子線の細胞死のメカニズムについて、DNAを直接切断する直接作用と、フリーラジカルを生成して障害を与える間接作用の割合が異なり、陽子線の方が直接作用の割合が大きいことが分かった。次に、湯之前事業推進本部長による講演では、陽子線治療における口腔ケアを行うために、医科歯科連携を行い、適正使用、新規運用まで成し遂げた貴重なお話を聞くことができた。湯之前さんは時系列で口腔粘膜炎の発生率が上昇した理由を考え、検証し、ウォーターサーバーの導入や、ステロイドの直前の静注から12時間前と2時間前の経口投与への変更などを行っていた。さらに、持留職員からも、先輩薬剤師として、そのキャリアパスについてご講演いただき、薬剤師免許を取得した後の自分の進路の選択肢が多いことを改めて実感した。てらわき薬局では、最新の機器を利用した調剤について実際に調剤室を見学することでその仕組みがよくわかった。また、入り口には時間外の薬の受け取り口があり、患者を第一に考えた薬局となっていることがよくわかった。実際、処方箋をもらって4日間の期限に間に合わず、処方箋を再発行してもらった経験があるので、このようなシステムを導入することでどのような患者にも確実に必要な薬を届けているのだと思った。また、グループワークでは対人業務には、患者さんと話し、薬学的な情報を入手すること、その情報を薬剤師として整理・解析すること、医師へのフィードバックをすることが重要であると学んだ。
⑫メディポリス国際陽子線治療センターでの講演や見学で、最先端の陽子線治療を学ぶことができました。センター長の荻野先生の講義では、がんの基礎的な知識から、陽子線が持つブラッグピークという性質を利用した陽子線の抗がん作用、メディポリスでの治療とホテル宿泊がどれほど便利で患者さんの負担軽減につながっているかについて知ることができました。陽子線は線量集中性が高く、さらに、頭頚部の悪性黒色腫の陽子線治療が、X線治療よりはるかに優れていることが示され、保険適用となったというお話がとても印象に残っています。また、乳がんの治療のために、独自でカップを作成して副作用を最小限にする工夫など、様々な取り組みもお聞きできてとても良かったです。実際に施設の患者さんが横になる治療台も拝見でき、回転したり、腫瘍の形に合わせて照射範囲が設定できたりするところを見せていただきました。さらに、その裏にある巨大なシンクロトロンや加速した陽子線を曲げるための巨大な磁石を拝見することができ、貴重な体験となりました。そして、数週間にわたって治療する必要のある患者さんが泊まるホテルは、景色も素晴らしく、岩盤浴、温泉、ジムなど多くの娯楽を楽しみながら豪華な食事も堪能できる素晴らしい施設でした。がん治療を受ける場合、本人やそのご家族は不安になることを予想し、その不安を取り除き、さらには陽子線治療をした期間を良い思い出にしてほしいという思いがあるというお話を聞き、とても感銘を受けました。薬剤師の湯之前先生のお話で、印象に残ったのが薬剤師の多職種連携の取り組みについてです。薬剤師という職にさらに可能性を見出せたとても貴重なお話でした。二日目の大賀薬局の見学では、分包の機械や必要な薬を正確に選択して膨大な薬の棚から選択する技術、患者さんが薬局が閉まっている時間でも薬を受け取れる仕組みなどについて初めて知ることができ、最先端の技術にとても驚きました。これらの機械化を通して対人業務を手厚くしていく必要があるというお話も伺え、これからの薬剤師の在り方について学ぶ貴重な経験となりました。
⑬萩野センター長の講義では、「がん」とがんの治療法の基礎から放射線治療と陽子線治療の違いや、実際に現場での治療法の選択について詳しくお話を聞くことができた。現在は放射線治療の方が認知度が高く、多く利用されているが、陽子線治療の方が治りやすい、副作用が出にくいというデータを知り驚いた。陽子線治療によるメリットは抗がん剤治療や外科的手術、放射線治療に比べ多くあるにも関わらず、その認知度の低さから陽子線治療があまり用いられておらず、最適な治療を受けることができていない患者がいるという現状は早々に解決する必要がある。学生の立場で陽子線治療の認知度を広める活動ができたらいいと思った。湯之前事務局長の講義では、薬剤師として現場の問題点を見つけ、その原因となるもの・事象を考え、それを改善し、問題が解決されたかを調査していることを知り、また、実際に問題が改善されているデータを見て、大学における研究活動で身につけていく力を、将来薬剤師としていかに生かすことができるか理解することができた。薬剤師の仕事は医薬品を扱う仕事のみでなく、患者や医療人のための資料作りなどもあり、改めて様々な業務を行うことができる職種だと思った。薬剤師の持留先生の講義では、湯之前事務局長の講義と同様に現場の問題点の改善例を知ることができただけでなく、持留先生の学校薬剤師としての活動経験を聞くことができた。私は病院・薬局で働くことしか考えていなかったが、学校薬剤師としてもまた違った角度で社会に貢献できたらいいなと思った。てらわき薬局城西では、液剤・散剤を包装する機械と医薬品管理を担う機械を見学することができた。特に、パソコンからデータを送るだけで処方したい医薬品が自動で出てくるだけでなく、同時に印刷されるシールに記載されたQRコードで在庫管理も行うことができること、さらにその自動で動く機械は対患者でも用いられ、処方箋などを登録しておけば、患者は24時間いつでも好きなときに薬局に医薬品を取りにくることができるというシステムには、衝撃を受けた。このシステムが全国で広まれば、医薬品も宅配のように、例えばコンビニエンスストアなど様々な場所で受けとることができるようになる未来も容易に想像できる。しかしあくまで、いくら最新の機械を導入しても使うのは人間であり、頭で考えて上手く使わなければ、薬局を効率良く、質良く運営するという目標は達成されないことを、自分が将来薬剤師になってからも忘れないようにしたい。